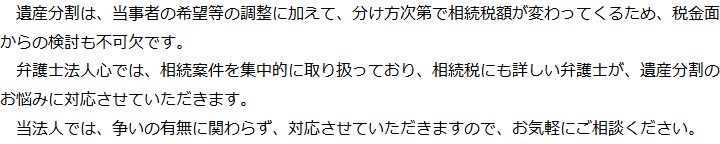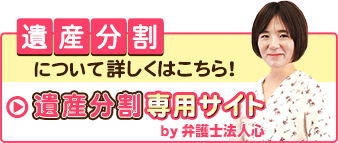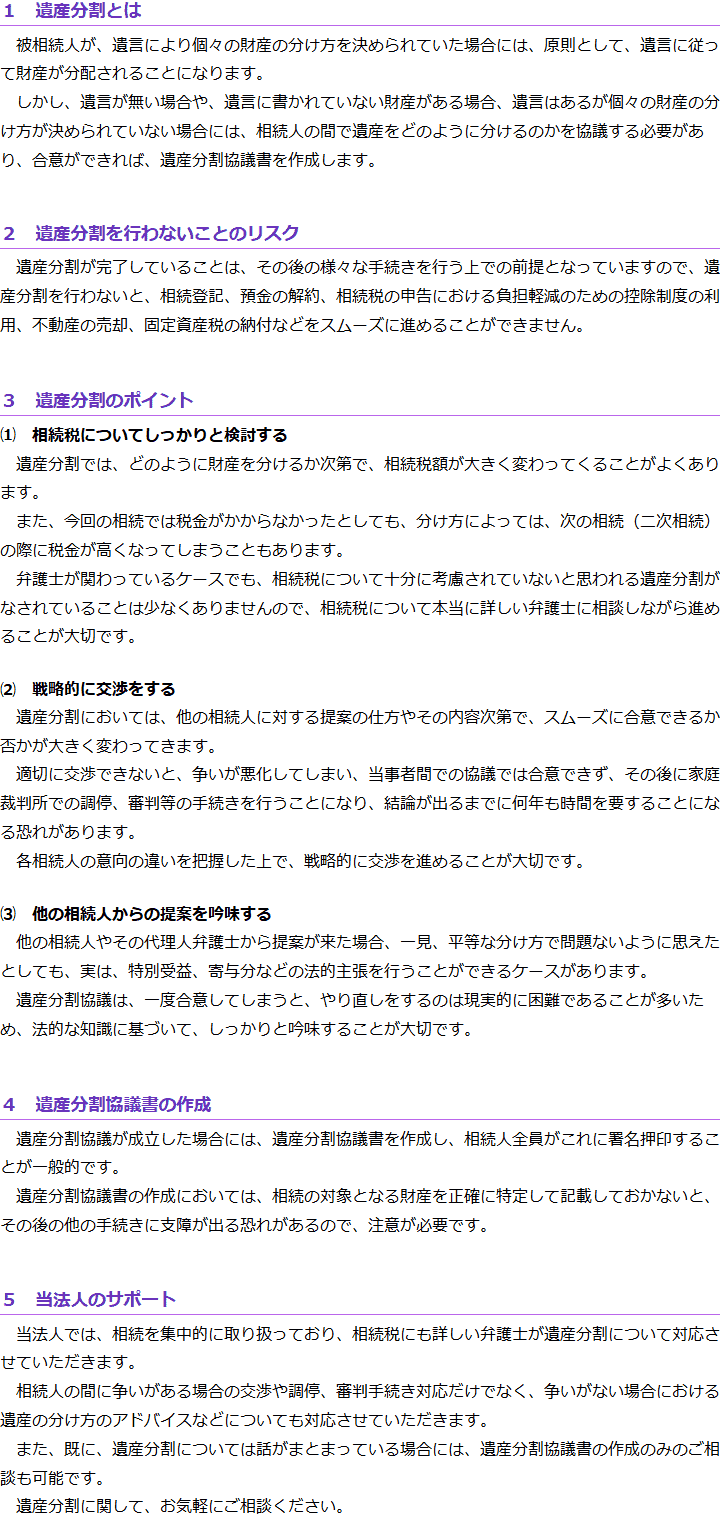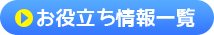遺産分割
お気軽にご相談を
京都駅から徒歩3分の場所に事務所があります。また、お電話・テレビ電話でのご相談も承りますので、遺産分割協議にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
遺産分割で気をつけた方がよいこと
1 遺言書があるかどうか
遺産分割を行う際、まず最初に遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書があれば、原則としてそれが尊重されるためです。
2 相続人が全員参加しているか

遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけません。
相続人が全員参加していない場合、遺産分割協議が無効になってしまうので、まずはきちんと相続人を調査して相続人を確定させることが大切です。
知っているつもりでも、調査の結果、新たな相続人が判明することもあります。
他の相続人が話し合いに応じない場合は、協議が進まないため、遺産分割調停、審判などの方法をとることになります。
また、相続人の一部が未成年者である場合や、判断能力が不十分な場合、行方不明である場合などは、親権者や特別代理人、未成年後見人、成年後見人、不在者財産管理人などの代理人が必要となります。
3 遺産・債務はどうか
遺産分割協議を行う際の遺産に漏れがあると、新たな遺産が見つかった場合に、再度遺産分割協議を行わなければならないため、きちんと確認する必要があります。
また、債務については相続人が承継することとなるため、これもあわせて調査を行います。
そのほか、たとえば、未登記建物や、預金から払い戻された現金などについて、遺産に含まれるのか否か、争いがある場合は、地方裁判所に訴訟を提起することとなります。
4 特別受益や寄与分について調整が必要かどうか
遺産分割において、法定相続分どおりで分けると、かえって不公平となる場合があります。
たとえば、多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合には、特別受益として相続財産に持ち戻したうえで相続分を決定したり、故人の介護や借金の肩代わりをした場合など、多大な貢献をした相続人がいる場合には、寄与分として、調整を行うことになります。
5 不動産の評価はどうか
遺産の評価として、預貯金などの金融資産については、明確にわかることが多いのですが、不動産については評価額にかなりの幅が出ることがあります。
そのため、各相続人において不動産の評価資料を出し合って、協議を行うことが多いです。
遺産分割の流れ
1 相続人の確定

遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があります。
そのため、まずは共同相続人が誰であるのかを確定させなければいけません。
相続人調査のために、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍のほか、共同相続人全員の現在戸籍を収集して、まずは共同相続人を特定することが必要になります。
2 協議内容をまとめる書類について
共同相続人が確定すれば、相続人の人数によって、遺産分割協議書を作成するのか、あるいは、遺産分割協議証明書(全員で1枚の紙を作成するのではなく、同内容が記載された複数枚を各共同相続人が作成します)あるいは相続分譲渡証書を作成するのかを判断します。
もし、共同相続人が多数である場合、1枚の遺産分割協議書に、共同相続人全員で署名捺印をすることは困難であるためです。
3 遺産分割の方法の確定
次に、遺産分割が必要な遺産の範囲や評価額を確定させます。
相続財産は、預貯金のように均等に分けやすい遺産ばかりとは限りません。
遺産の中に不動産や株式が含まれる場合は、その価値を評価しなければいけませんので、不動産の評価や自社株式の評価、上場株式の評価時点を話し合うことになります。
その上で、遺産の分割割合、すなわち、誰がどの程度遺産を受け取るのかを決めていきます。
遺産分割の方法は、財産をそのままの形で分割するのか、売却してその金額を分割するのかなど、いくつか方法があります。
どのような形で遺産分割をするのか、相続人全員で協議を行います。
4 協議書等の作成
これまでの遺産分割協議で決まった内容について、遺産分割協議書等の書類を作成し、相続人全員が実印で署名捺印することで、遺産分割は完了となります。
5 調停の申立て以降の手続き
万が一、遺産分割の協議が整わなければ、家庭裁判所に対し、遺産分割の調停を申し立てます。
調停の手続きでは、共同相続人らから事情を聴いたり、遺産についての鑑定を行ったりした上で、家庭裁判所から解決案の提示を受けるなどして、家庭裁判所の仲介により、合意に向けた話合いが進められます。
話合いがまとまれば調停が成立し、遺産分割は完了となります。
また、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審判として、遺産分割についての判断をすることになります。
裁判官の審判の結果に不服があれば、高等裁判所に対して即時抗告の申立てが可能です。
遺産分割について専門家に依頼した場合の費用
1 資料を集めるための費用

遺産分割のゴールの1つは、預貯金の解約や、不動産の名義変更などの相続手続きを完了させることです。
相続手続きを行うために必要な資料がいくつかあり、その資料を集めるための費用が必要になります。
例えば、相続手続きでは、被相続人の方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。
この戸籍謄本を役所で取得する場合、1通あたり450円か750円の費用がかかります。
これらの必要経費は、専門家に依頼したかどうかに関係無く必要になります。
専門家にこれらの資料の収集も依頼した場合は、その収集自体に手数料が発生する場合があります。
この手数料について、書類1通あたり2000円といったように定めている事務所もあれば、相続手続きに必要な戸籍収集全体で5万円といったように定めている事務所もあります。
2 合意書を作成するための費用
相続人同士で遺産の分け方についての争いは無く、当事者同士で遺産分割協議が合意に至った場合に、遺産の分け方の合意書の作成のみを専門家に依頼するというケースもあります。
遺産の分け方の合意書は、預貯金の解約の際に銀行に提出したり、不動産の名義変更の際に法務局に提出したりします。
合意書の作成を専門家に依頼した場合には、その難易度や記載すべき内容の量に応じて、数万円から20万円程度の費用が必要になることが多いです。
3 遺産分割の交渉を依頼した場合
相続人同士で争いがある場合や、面識の無い相続人を探し出して話をする場合のように「遺産分割の交渉」を弁護士に依頼するための費用については、大きく2段階に分かれています。
1つは、交渉を依頼するにあたって支払う「着手金」という費用です。
着手金は、交渉そのものへの対価なので、交渉が成功したかどうかに関係なく支払いが必要になります。
もう1つは、「成功報酬」です。
成功報酬は、交渉の結果得られた財産に対して発生する報酬なので、得た財産の何%かが専門家の報酬になります。
もっとも、事務所によっては、着手金がない事務所もあります。
また、成功報酬も事務所によって異なります。
そのため、遺産分割協議を弁護士に依頼する場合は、着手金や成功報酬について事前にしっかり確認しておくとよいかと思います。
遺産分割に納得がいかない場合の対応
1 遺産分割の方法に納得いかない場合

例えばお父さんが亡くなり、遺産として1000万円の預金と、1000万円の株式が残されたとします。
相続人は長男と長女の2人で、長男が長女に対し「長男が株式を相続するから、長女は預金を相続すればいい。金額的には平等な相続になるはずだ。」と主張した場合で、実は長女も株式が欲しいケースを考えてみます。
このような場合、長女はどのような対応をすべきでしょうか。
長男と遺産分割で揉めたくないから等の理由により安易に譲歩してしまうと、後になって大きな損をしてしまう可能性があります。
たとえば、その後株式の価格が大きく値上がりして1500万円の価値になれば、株を相続した方が500万円得をしたことになってしまいます。
そのため、相手の主張をそのまま受け入れるのではなく、遺産分割の方法について交渉をする必要があります。
2 一部の相続人が生前贈与を受けている場合
例えば遺産が1000万円の預金のみで、相続人が長男と長女だった場合、通常であれば500万円ずつ預金を分けることになります。
しかし長男が400万円の生前贈与をうけていた場合、トータルで見ると、長男が遺産500万円と生前贈与400万円の合計900万円を取得し、長女は遺産500万円を取得したことになるため、不公平さがあります。
このようなケースでは、遺産分割を行う際に、生前贈与も考慮した上で預金の取得割合を決めたいという交渉をすることになります。
3 亡くなった方への貢献度が反映されていない場合
例えば長男が寝たきりの父親と長年同居し、ずっと介護をしていたような場合や、長男が父親に多額の仕送りをしていたような場合を考えてみます。
こうした場合には、長男の父親への貢献度を、遺産の分け方に反映させるべきです。
相続人同士の話し合いでそういった貢献度が無視されてしまっている場合は、その貢献度をアピールして遺産の分け方を決める必要があります。
4 不動産の評価が不当な場合
例えば遺産として実家と預金1000万円があり、相続人が長男と長女だった場合を想定します。
実家を売却すれば3000万円の値がつくにもかかわらず、長男が「実家は自分が相続する。実家の価値は200万円なので、預金を400万円もらう。」と主張してきた場合、このままでは平等な遺産分割とはいえません。
長女は不動産の評価方法がおかしい旨を交渉して、預金の取り分の交渉をする必要があります。
遺産分割協議書を作成する際に注意すること
1 遺産分割協議書を作成する意味

そもそも遺産分割協議書を作成しなければならないかというと、法的な義務はないものの、遺産分割協議書は作成しておくべきといえます。
なぜかというと、遺産分割に関して相続人の間で合意が成立した場合、遺産の名義を変更するために諸機関に提出したり、後の紛争を予防したりするためです。
例えば、遺産には、不動産や金融資産が含まれる場合が多くあります。
それらを相続して名義の変更を行う際、登記所や銀行等に対し、誰がどの遺産を手に入れたのかを証明する必要がありますが、遺産分割協議書は、そのような場合に活用することができます。
また、相続人が話し合って遺産分割協議をしても、口頭で合意しただけでは、後で紛争になった際に元々の合意内容を証明することが困難になります。
そこで、後の紛争を予防するため、誰がどの遺産を手に入れたのか明確に記載して書面にした遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
2 遺産分割協議書を作成する際の注意点
① 遺産と取得者を特定すること
誰がどの遺産を手に入れたのかを明記する必要があります。
手に入れた遺産については、それを特定するに足りる事柄を、できるだけ詳細に記載しておく必要があります。
② 新たに遺産が見つかった場合の取扱いを盛り込んでおくこと
たいていの場合、遺産分割協議は遺産を調査した上で行うものですが、遺産分割協議が成立した後で、新たに遺産が見つかることがあります。
新たに遺産が見つかると、その遺産について再度遺産分割協議をしなければならず、その過程で新たなトラブルが発生しないとも限りません。
このような場合に備え、新たに見つかった遺産をどのように処理するのか、あらかじめ遺産分割協議書に盛り込んでおくとよいです。
例えば、相続人らで改めて、新たに見つかった遺産の分割協議をすることを定めるほか、あらかじめ、相続人の誰かが手に入れることを決めておくことなどが考えられます。
③ 住所は住民票や印鑑証明書に記載のとおりに記載すること
登記所や金融機関に提出する場合、記載内容に少しでも不備があると、記載の修正や再提出を求められる可能性があります。
そうなると、相続人らが改めて書面を作り直すなど、新たな手間が生じてしまいます。
それを避けるため、住所は、住民票や印鑑証明書に記載されたとおりに記載することが必要です。
④ 実印を押印すること
すべての相続人が遺産分割協議の内容に同意していることを証明するため、実印を押印して印鑑証明書を添付します。
⑤ 銀行や証券会社等から、あらかじめ専用の書式を取り寄せておくこと
銀行や証券会社等によっては、遺産分割協議書のほかに、金融機関ごとの専用の書式に相続人らの署名押印を求めるところがあります。
遺産分割協議書への署名押印の機会に合わせて各金融機関の専用の書式に対しても署名押印ができるように、あらかじめ金融機関への確認や専用の書式の取り付けなどの準備をしておくとよいです。
⑥ 作成通数について
遺産分割協議に参加した相続人が1人1通ずつ持つことができるように、遺産分割協議書は、相続人と同じ通数を作成するべきです。