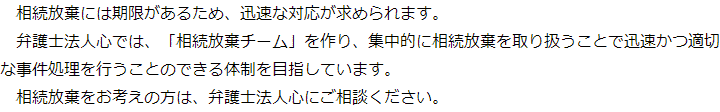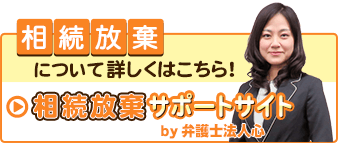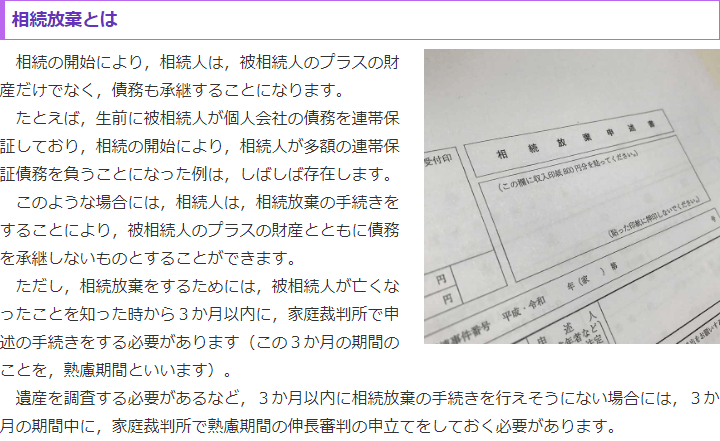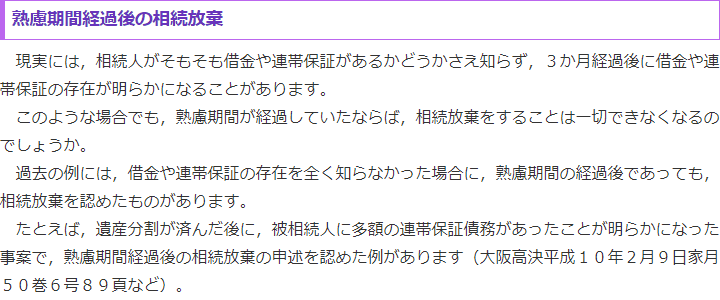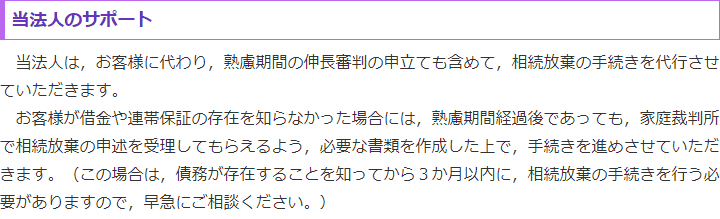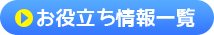相続放棄
事務所所在地について
京都駅の近くに事務所がありますので、相続放棄のご相談の際にもお越しいただきやすいかと思います。詳しくはこちらからご確認ください。
相続放棄の方法
1 法律上の相続放棄

相続人間の遺産分割協議で、財産を取得しない場合に、「相続放棄する」といった表現を用いることがありますが、それは法的な意味での相続放棄ではありません。
この場合ですと、相続財産の中に債務があれば、債権者から請求を受けることになります。
そのため、債務も含めて一切の財産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きを行わなければなりません。
2 相続放棄の期限
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。
ただし、財産を調べるのに時間が必要な場合には、相続放棄の期間を伸長する手続きをとることができます。
また、3か月を過ぎてしまった場合でも、例外的に相続放棄が認められることもあります。
たとえば、生前にまったく交流がなかった方について、債権者から通知がきて初めて、死亡した事実や債務があることを知るようなケースでは、3か月以内に相続放棄の手続きをとることが困難であることも少なくありません。
そういった場合は、あきらめずに専門家に相談するとよいでしょう。
3 相続放棄の検討
相続放棄を検討した方がよいケースとしては、借金などマイナスの財産が大きい場合や、他の相続人とトラブルが見込まれ、関わり合いを避けたい場合などが挙げられます。
財産の状況がよくわからない場合、調査をおこなってから方針を決めることもありますが、調査ですべて明らかになるとは限らないため、費用対効果を考えて、リスク回避のために相続放棄を行うということもあります。
しかし、いったん相続放棄を行うと撤回ができないため、よく検討して判断する必要があります。
なお、相続財産を一部でも処分すると、相続放棄が認められなくなるため、その点も注意が必要です。
4 相続放棄の申述と必要な書類
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、必要書類を提出して行う必要があります。
相続放棄を行う際、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本や住民票除票(又は戸籍の附票)、相続放棄をする人の戸籍謄本、相続放棄の申述書が必要となります。
そのほか、相続放棄の申述をする人と亡くなった方の関係によって、必要な書類が異なります。
配偶者や子は、相続放棄の必要書類は比較的少ないのですが、直系尊属や兄弟姉妹の場合や、代襲相続人(亡くなったからみて孫や甥姪が相続権を持つ場合)の場合には、必要書類が多くなるため、書類を集めるのに時間がかかる傾向にあるといえます。
5 相続放棄の受理
裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出すると、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届き、手続完了となります。
これに対し、裁判所が本人に対し、相続放棄の意思に間違いがないかどうかを確認するために、必要に応じ、相続放棄照会書を送る場合もあります。
このような照会書が届いたら、すみやかに回答を記入して、期限内に返送しましょう。
照会書と回答書の内容に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送付され、手続完了となります。
相続放棄の流れ
1 相続放棄をするかどうかの判断

相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務の一切を受け継がないものです。
相続放棄は、相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所にそのことを申述しなければならないと定められています。
被相続人が亡くなったことや、自分よりも順位が高い相続人が相続放棄をしたことなどを知ることで、自分自身が相続人になったことを知ることになります。
相続人になったことを知った時、相続する財産や債務がどれだけあるかによって、相続放棄するかどうかの判断をすることになります。
相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなりますので、相続放棄をすべきかどうかは慎重な判断が求められます。
相続放棄をするかどうかや、相続放棄のやり方や注意点等について弁護士が相談にのらせていただきますので、不安な場合は弁護士にご相談ください。
2 家庭裁判所に申述するまでの手続
自分以外の相続人や、被相続人との関係を把握するため、必要となる戸籍謄本や除籍謄本等を取り寄せます。
そして、申述書を作成し、家庭裁判所に必要書類とともに提出します。
申述書の提出先である家庭裁判所は、被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所になります。
例えば、被相続人の最後の住所地が京都市であった場合には、京都家庭裁判所が管轄裁判所となります。
参考リンク:裁判所・京都府内の管轄区域表
弁護士に手続を依頼していれば、以上の一連の手続を弁護士が担当することになります。
3 家庭裁判所による申述の受理
家庭裁判所が申述を受理することにより、相続放棄が認められます。
その前に案件によっては、家庭裁判所から、相続人になったことを知った事情など、相続放棄をするに至った事情について照会されます。
弁護士に手続を依頼していれば、その照会は相続人の連絡先に直接来るか、弁護士の事務所に来るかしますので、いずれにしても弁護士と打ち合わせて答えることになります。
そして、必要な場合があれば、家庭裁判所に申請をすれば、相続放棄の受理証明書を発行してもらうことができます。
相続放棄の期限
1 相続放棄は時間との勝負

相続放棄は、相続手続きの中でも最も期限が厳しい手続きの1つです。
相続放棄の手続きの期限は、たったの3か月しかありません。
3か月の間に、相続放棄をすべきかどうかを検討しなければいけません。
検討するためには、まず相続財産の全容を明らかにしなければいけませんが、相続財産の調査に思いのほか時間を要することもあります。
ご家族が亡くなった後は、色々と慌ただしい日々が続いたり、悲しみに暮れて何もやる気が起きないという期間があったりと、相続放棄に取りかかることが難しいケースも多いかと思います。
そうしている間に、3か月の期限が間近に迫ってしまうということも考えられますので、相続放棄を検討している場合は、まずは迅速に行動することが重要です。
2 3か月の期限はいつから始まるのか
それでは、その3か月の期限というのは、いつから始まるのでしょうか。
多くの方が、亡くなった日から3か月で期限がくると思っているかもしれません。
しかし、相続放棄の期限は、厳密には、「亡くなったことを知ってから」3か月です。
どう違うのだろうと思われるかもしれませんが、例えば、ご家族がご自宅で孤独死した場合には、しばらくの間、亡くなったことが誰にも知られない状態が続くこともあります。
仮に、亡くなってから2か月後に、ご遺体が発見されたような場合、期限が残り1か月しかないとなると、あまりにも時間の余裕がなくなってしまいます。
そこで、相続放棄の期限は、亡くなったことを知った日から3か月とされています。
3 自分よりも優先的な相続権を持っている人がいる場合
相続権には順位があります。
第1位の相続権を持つのは子で、第2位が親、第3位が兄弟姉妹です。
第2順位以降の相続人は、第1順位の相続人が存在しないか、第1順位の相続人が全員相続放棄をして初めて相続権を持ちます。
相続権がなければ、そもそも相続放棄ができないため、第2順位以降の相続人は、ご家族が亡くなったことに加え、「自分が相続権を持つことになったこと」を知った日から、3か月の期限がスタートします。
単純に、ご家族が亡くなったことを知っただけでは、相続放棄の期限はスタートしません。
4 3か月が経過しても相続放棄できる場合がある
例えば、父が亡くなり、遺産も借金もほとんどなかったため、何も相続手続をしなかったというケースは珍しくありません。
しかし、実は父が借金をしており、亡くなって1年が経過した後、その請求が子に届いた場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、父が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから、3か月が経過しているため、もう相続放棄ができないようにも思えます。
しかし、裁判所は、このようなケースでも相続放棄を認めることがあります。
そのため、すでに3か月が経過している場合でも、相続放棄を行うことをあきらめずに、専門家に相談することが大切です。
相続放棄の手続きにかかる費用
1 収入印紙代

相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出する手続きです。
裁判所に相続放棄の書類を提出する場合、手数料を納めなければなりません。
手数料の支払方法は、現金の手渡しや振込ではなく、収入印紙で行います。
つまり、相続放棄の書類に800円の収入印紙を添付することで、手数料を納めます。
2 戸籍の取得費用
相続放棄をする際は戸籍の提出が必要です。
必要となる戸籍は、相続放棄をする人と被相続人との関係によって変わってきます。
例えばお父さんが亡くなって、長男が相続放棄をする場合、まずはお父さんが亡くなったことを証明するために、お父さんが亡くなった旨の記載がある戸籍謄本が必要です。
次に長男が親子関係を証明するために、長男の戸籍も必要です。
戸籍は、市区町村役場で取得することになるので、その取得の際に費用が必要です。
戸籍の取得には、種類によって450円と750円の費用がかかります。
3 亡くなった方の住所が分かる資料
相続放棄をする場合、家庭裁判所に書類を提出しますが、どの家庭裁判所でもいいというわけではありません。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
そのため、亡くなった方の最後の住所地を証明するために、住民票(除票)または戸籍の附票が必要です。
これらの資料も、戸籍と同じく市区町村役場で取得することになります。
その取得費用は市区町村ごとに異なりますが、200円から400円ほどの費用がかかります。
4 専門家に依頼した場合の費用
相続放棄の手続きを専門家に依頼した場合、一定の費用がかかります。
まず、相続放棄の相談をした際の相談料がかかる場合があります。
相談料を無料としているところや、初回30分無料としている事務所もありますので、相談料の有無はホームページなどでご確認ください。
また、相続放棄の手続きを依頼した場合にはその手数料がかかります。
この費用は一律で決まっているわけではなく、各専門家が自由に設定できるようになっています。
そのため、相続放棄手続きにかかる手数料は事務所によって様々です。
また、相続放棄の依頼内容に債権者対応や戸籍収集などが入っているかどうかによっても手数料が異なります。
相続放棄を依頼した場合の費用について、いくらかかるのか、対応範囲はどこまでかを、契約前にしっかりと確認しておくことが大切です。
不明点等がないように、疑問等がありましたらご相談の際に確認されることをおすすめします。