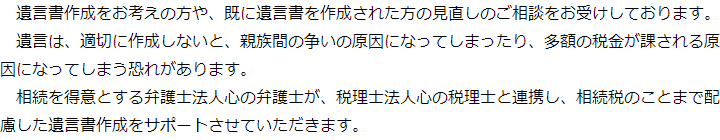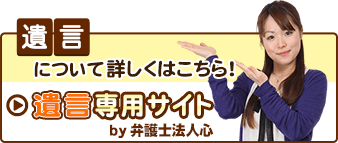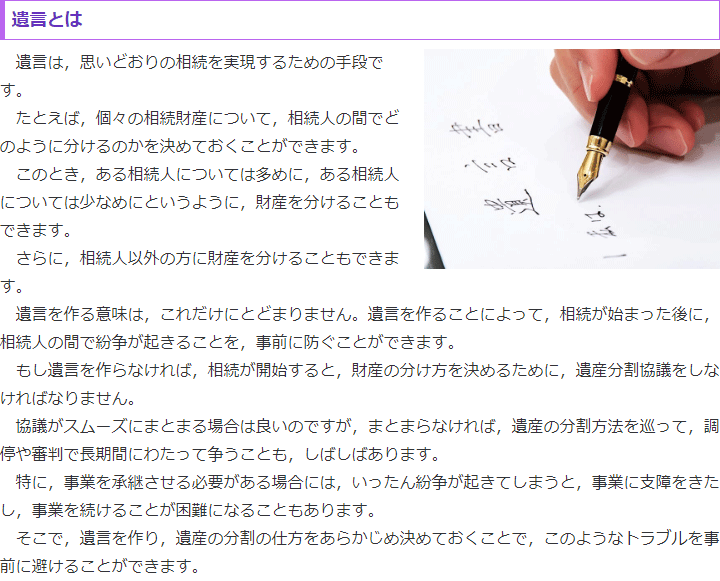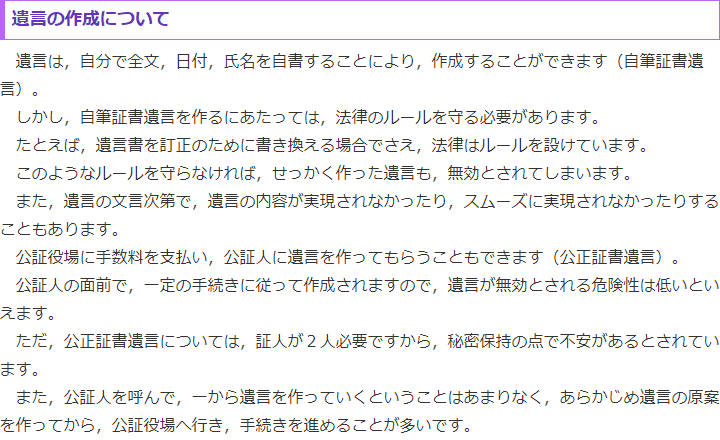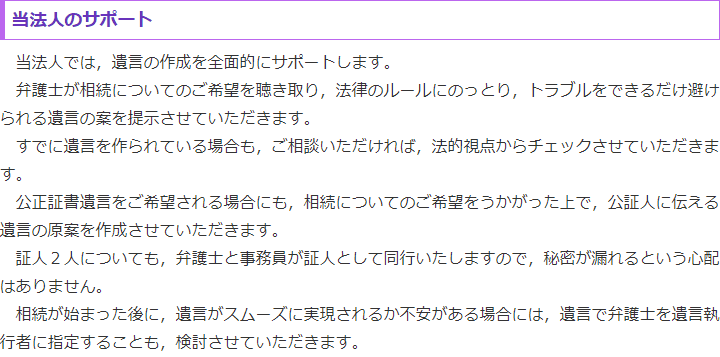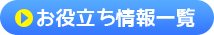遺言
事務所所在地について
来所いただく際のご負担を少しでも軽減できるように、最寄り駅の近くという利便性のよい立地に事務所を設けています。遺言に関するお悩みは、私たちにご相談ください。
遺言を作成する際の注意点
1 ご自身で遺言を作る際に必ず守るべき要件

自筆証書遺言を作成される場合に必ず守るべき要件は、以下のように民法によって定められています。
① 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し、押印すること
② 自書ではない財産目録が添付されている場合、全てのページに署名、押印すること
③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印すること
2 遺言が無効になる場合
作成された遺言が上記の要件を満たしていなければ、その遺言は無効になり、相続の手続きの時に使えなくなります。
例えば、遺言書の本文や付言事項をパソコンで作成して、署名押印だけを自書しているような場合、その遺言は無効になります。
一方、遺言書の本文や付言事項をご自身で書くことが難しく、他の人に添え手をしてもらって書いた場合も、その遺言が無効かどうか争われるおそれがあります。
また、日付、氏名、押印のいずれか一つを欠いても、その遺言は無効になる可能性があります。
日付は特定さえできれば、必ずしも年月を記す必要はなく、遺言作成の日が暦の上で明らかになればよいとされています。
例えば「満60歳の誕生日に」や、「何年の先祖祭の日に」という記載でもかまいませんが、疑義を生じさせないためには、きっちりと西暦か和暦で作成した方が無難かと思います。
他方、「7月吉日」などと記載すると、日付の特定ができず、遺言は無効になってしまいます。
また、全く氏名が書かれていない場合、その筆跡から本人の自筆であることが明らかになったとしても、遺言は無効になります。
そして、遺言書の書き間違った箇所が訂正されているのにもかかわらず、訂正した旨の記載や、訂正又は追加した箇所への押印が漏れているような場合、パソコンで作成した財産目録に署名、押印が漏れているような場合、パソコン等で作成した財産目録を印刷してその余白に遺言書の本文を自書するような場合も、いずれも遺言が無効になるリスクがあります。
3 遺言の作成については専門家にご相談を
このように、遺言を作成する際には注意しなければならない点があり、また、相続人に引き継ぐ財産についてもよく考えておく必要があります。
ですので、遺言を作成される際は、遺言に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
遺言作成を依頼する専門家選びのポイント
1 個別的な対応が可能な専門家かどうかをチェック

遺言は、ある程度の法律知識があれば、作成自体はそれほど難しくはありません。
また、専門書の中には、遺言書のひな形が記載されたようなものもあるため、それを見ながらであれば、一応法的に有効な遺言の作成は可能です。
しかし実際には、形式的に有効な遺言であっても、内容に問題があり、かえってトラブルを引き起こす原因になってしまう場合も少なくありません。
私たちに相続のご相談をいただく場合も、遺言の内容に問題があり揉めてしまっているといった相談もよくあります。
ではどういったケースで、どのような内容の遺言が適切なのかについては、千差万別で、ひとくくりにはできないことが多いです。
例えば、遺産の中に不動産がある場合、誰に、どのような形で不動産を相続させるべきなのかは、家族構成、家族の住居地、家族の収入状況などで変わってきます。
家族全体の個別事情をしっかりと把握した上で、最適な遺言を作成することが大切です。
そのようなことを考慮しながら遺言を作成しようと思うと、相続に関する知識が必要になってくるかと思いますので、専門家にご相談ください。
その際、専門家であれば誰でもいいというわけではなく、上で述べたように、個別事情を把握した上で適切な遺言書作成に対応してくれる専門家を選ぶことが大切です。
2 万が一を想定した提案ができる専門家かどうかをチェック
遺言を作成する上で欠かせないのが、「万が一」を想定することです。
例えば、「長男に不動産を相続させる」という遺言を書いたとしても、万が一、長男が先に亡くなってしまった場合は、どうなるのかということを考えます。
この場合、不動産を誰に相続させるのかは、遺言に書いていないことになってしまいます。
そのため、相続人同士で、不動産を誰が相続するのかを話し合わなくてはならず、余計な紛争を招く可能性があります。
このように、遺言を作成する際は、万が一を想定することが重要です。
3 遺言に関する裁判に詳しい専門家かどうかをチェック
遺言を作っても、必ずしも安心とはいえません。
遺言者に遺言能力がなければ、その遺言は有効とは認められないことがあり、遺言が無効だという裁判が起きてしまう可能性があるためです。
例えば、「判断能力がない高齢者に、無理やり遺言を作成させた」という主張が予想される場合を想定します。
遺言の有効性について、裁判を経験している専門家であれば、どういった証拠があれば、遺言の有効性を証明できるのかを熟知していますので、遺言を作成する際に、医師の診断書を取得しておいたり、遺言を作成する様子を録画しておいたりするなどの対策を取ることになります。
どのような証拠があれば、遺言の有効性を証明できるのかは、遺言に関する裁判を扱っている専門家でなければ判断が難しい部分です。
そのため、遺言を作成する際は、遺言に関する裁判に詳しい専門家にご相談ください。
自分で遺言を作成するメリット・デメリット
1 自分で遺言を作成すると費用が安い

ご自身で作成する遺言のことを、自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は、字を書ける方であれば簡単に作成できるため、特別な費用はかかりません。
そのため、筆記用具と用紙さえ用意できれば、いつでも、どこでも費用をかけずに遺言の作成が可能です。
なお、筆記用具や用紙に決まりはありませんが、改ざんの防止や、間違って破棄してしまうことを避けるため、鉛筆を使ったり、チラシの裏に記載したりすることは避けたほうがよいかと思います。
2 形式面で無効になってしまうリスク
自筆証書遺言の書き方は、法律で定められています。
例えば、「自筆でなければならない」「日付が特定できなければならない」といったルールがあります。
これらの形式的なルールを守れていない自筆証書遺言は、無効になってしまうリスクがあるため、注意が必要です。
3 相続の手続きができないリスク
自筆証書遺言は、作成するだけでは意味がありません。
相続が起きた後に、その自筆証書遺言で相続の手続きができないと、目的を達成することができません。
相続の手続きとは、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約などを指します。
しかし、例えば「京都の不動産を、長女に相続させる」といった内容の自筆証書遺言ですと、不動産の特定ができないため、相続登記ができない可能性があります。
そのため、自筆証書遺言を作成する際は、相続後の手続きができるような内容にする必要があります。
4 遺言作成は専門家への相談をおすすめします
自筆証書遺言は、いつでも、どこでもお手軽に作成できるというメリットがあります。
他方で、形式面に不備があると、せっかく作成した遺言が無効になったり、本来の目的が達成できなくなったりするリスクがあるなど、デメリットもあります。
また、せっかく作成した遺言が、相続後の相続人同士のトラブルの原因となってしまうと作成した意味がありませんので、「万が一相続人が先に亡くなった場合にはどうするのか」といったことや「自筆証書遺言を使って名義変更などの手続きを行う役割を誰に任せるのか」といったことも検討しなければなりません。
どのような内容の遺言だとトラブルになりやすいのかについては、相続に詳しくないとなかなか把握することが難しいかと思います。
そのため、ご自身で遺言を作成する場合であっても、専門家に相談することが大切です。
遺言をはじめ、相続を得意とする者がご相談を承り、遺言作成のサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺言執行者の役割
1 遺言執行者の役割とは何か

遺言執行者の役割は、遺言に記載された内容を実現するために、相続財産の管理やそのほか遺言の執行に必要な手続きを行っていくというものです。
遺言で遺言執行者が定められている場合、遺言執行者のみが遺贈の履行を行うことができ、相続人は遺贈の履行を行うことはできません。
また、相続人は、遺言執行者が行う相続財産の処分など、遺言の執行を妨げることはできません。
このように、遺言執行者は、遺言の内容を実現するために執行するという役割を果たすために、相続人との関係でも権限が強化され、明確化されています。
遺言で遺言執行者が定められていない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、遺言執行者を選任してもらうことができます。
2 遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者は、任務を開始したあとは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する必要があります。
相続人の調査や相続財産の調査を行い、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する必要があります。
遺言に遺言執行者の権限などを正しく記載しておけば、遺言執行者は、遺贈、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しや分配などを行うことができます。
遺言に記載されていた内容を実行したら、相続人に対し、任務完了報告を行います。
以上の任務について、遺言執行者は、自己の責任で、第三者に任務を依頼することができるものとされています。
3 遺言執行者の欠格事由・解任・辞任
遺言執行者は遺言の内容を実現すべき任務を担うため、誰でもなれるというものではありません。
未成年者や破産者は、遺言執行者になることができません(欠格事由)。
また、遺言執行者が任務を怠ったときや横領などの不正を行ったときは、利害関係者が家庭裁判所に対し、遺言執行者を解任するよう請求することができます。
これに対し、遺言執行者は、遺言の内容を確認したあと、就任する前であれば、遺言執行者への就任を拒むことができますが、いったん就任したあとに辞任するためには、正当な事由が必要となります。
4 遺言執行者の中立性
遺言執行者は、中立的立場で任務を遂行することが期待されているので、相続人間に争いがある場合は、特定の相続人の代理人となることは慎まなければならないとされています。