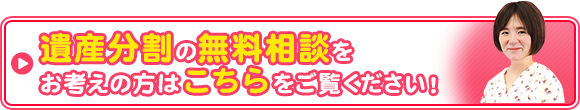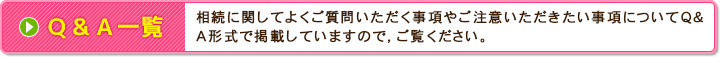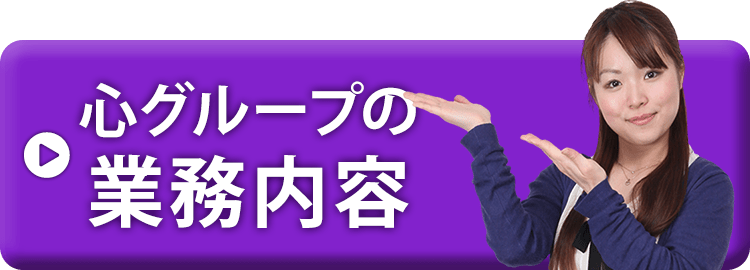遺産分割における不動産評価の重要性
1 遺産分割における不動産評価
遺産分割を行う際、不動産の評価を行うことは非常に重要な意義を持ちます。
今回は、なぜ遺産分割において不動産の評価を行うことが重要なのかという点について解説を行っていきたいと思います。
2 遺産分割の流れ
⑴ 全体像
遺産分割を行う際、通常は以下のような流れで行っていきます。
① 相続人の確定
② 遺産の範囲の確定
③ 各遺産の評価
④ 分割する財産の確定
この内、不動産評価は③の段階で行っていきます。
⑵ 具体例
例えば、以下のような遺産を、相続人A、B、Cの3人で分割していく場合を想定します。
<遺産>
預貯金 2000万円
不動産① 自宅の土地・建物(固定資産税評価額合計2000万円)
※この自宅にはAが居住している。
不動産② 賃貸物件の土地・建物(固定資産税評価額合計2000万円)
この時、Aは不動産①にこれからも居住していきたいと考えているため、不動産①の取得希望を行うことが多いでしょう。
しかし、この不動産を固定資産税評価額通りの評価で取得してしまうと、法定相続分である3分の1に相当する金額を取得することになってしまうため、一切預貯金を受け取ることができないことになってしまいます。
Aとしては、今後の生活費等も考えると少しは預貯金を受け取れたほうが良いと考えるため、不動産の評価額を減らす方向性で主張する可能性があります。
そのため、例えば自宅の前の道路の幅が細く交通の便が悪い点や、近くに河がある影響により地盤が緩い等の点を指摘して不動産の評価額を下げる方向性で主張をして、不動産①は時価額で1500万円程度の価値しかないという形で主張していくことになります。
反対に、Bは、預貯金の全額とあわよくば不動産を取得した人から代償金等の金銭を受け取れた方が自身に有利であるため、不動産①の評価額が実際より高いことを主張していくことになります。
例えば、不動産①は特急電車が泊まる主要駅から徒歩5分程度の場所に所在していることや、家屋が築浅である点等を主張し、2500万円程度の価値があることを主張していく事になります。
⑶ 小括
このような状態で、不動産②の評価額については特に争いが無く、Cが不動産②の取得希望を出していた場合、ABそれぞれの主張が認められた場合について検討します。
<Aの主張が認められた場合>
不動産①は1500万円として評価されるため、遺産総額としては、5500万円となります。
この時の各人の法定相続分は、5500万円÷3=18,333,333円(小数点以下切り捨て)となります。
そして、Aの取得額に足りない分は18,333,333円-15,000,000円=3,333,333円となり、その金額を2分の1にした1,666,666円をBCがそれぞれAに対して支払うことになります。
<Bの主張が認められた場合>
不動産①は2500万円となるため、遺産総額としては6500万円となります。
この時の各人の法定相続分は、6500万円÷3=21,666,666円(小数点以下切り捨て)となります。
そして、BCの取得額に足りない分は21,666,666円-20,000,000円=1,666,666円となり、AはBCに対して各1,666,666円ずつ支払うことになります。
⑷ 結論
このように不動産①の評価額について誰の主張が採用されるかによって、遺産分割の結論が大きく異なってくることになります。
そのため、遺産分割においては不動産の評価額をいくらにするのかが重要といえるでしょう。