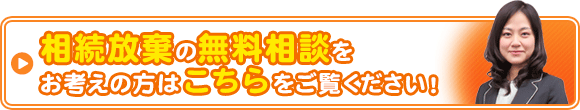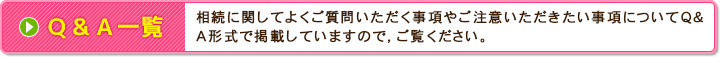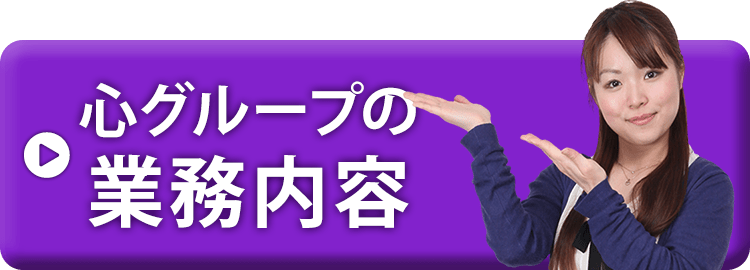相続放棄の熟慮期間
1 相続放棄の熟慮期間とは
ご家族が亡くなった際には、遺産を相続するのか、それとも相続の権利を放棄するのかを決断しなければなりません。
遺産の中で、資産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄を検討することになるかと思います。
また、借金は無いものの、不要な土地を受け継ぎたくない場合や、他の相続人と疎遠になっている等の理由から遺産分割のための話し合いをしたくないという場合も、相続放棄を検討することになります。
しかし、相続放棄をするかどうかをいつまでも決めないままでいると、他の相続人や債権者が困ってしまいます。
そのため、相続放棄をするかどうかは、自分が相続人となる相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決めないといけないというルールがあります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
2 相続放棄の熟慮期間中に行うこと
相続放棄をするかどうかの選択は、どのような遺産があるかによって、大きく左右されます。
そのため、まずは遺産の調査を行う必要があります。
亡くなった方が不動産を所有していれば、固定資産税に関する通知が家に届いているはずですので、その通知を確認します。
もっとも、固定資産税に関する通知には、全ての不動産が記載されているとは限らないため、注意が必要です。
また、亡くなった方の家やお部屋、財布の中などを探すと、通帳やキャッシュカードが見つかる場合も多いはずです。
見つかった通帳やキャッシュカードなどを元にして、どの銀行に、どれだけの預貯金があるのかを調査することになります。
3 借金の調査も必要
もし、亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合、相続放棄が必要になる可能性が高くなります。
借金の有無の調査をするためには、家に請求書が届いているかどうかや、通帳の取引履歴をチェックすることが有効です。
また、信用情報機関に問い合わせをすることで、借金が残されているのかどうかをある程度明らかにすることができます。
4 熟慮期間の延長も視野に
上記のような調査のためには、相応の時間が必要になります。
場合によっては、3か月以内に調査が終わらないこともあるかもしれません。
その場合は、熟慮期間の延長を行うことができます。
ただし、熟慮期間の延長は、家庭裁判所で行う必要があります。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
熟慮期間の延長に際しては、その必要性について、裁判所にしっかりと説明しなければなりません。
5 熟慮期間中に注意すること
熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄することができなくなってしまうことはもちろんですが、たとえ熟慮期間内であっても、相続財産を処分するなどの行為をしてしまうと、単純承認、つまり相続をする意思があるとみなされ、相続放棄することができなくなってしまいます。
単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなる場合について、具体的にはこちらをご参照ください。
相続放棄を検討している場合には、この点にも注意が必要です。
6 相続放棄についてのご相談
相続放棄をすると決めた場合には、3か月の熟慮期間内に必要な書類をそろえたうえで家庭裁判所に申立てまで行わなければなりません。
相続放棄の流れについては、こちらでもご説明していますので、参考にしてください。
財産や債務の調査に時間がかかっているなど、相続放棄の期限にお悩みの方や、熟慮期間の延長をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
相続放棄をする場合も、熟慮期間の延長をする場合も、3か月以内に家庭裁判所に必要な書類をそろえて申立てを行わなければならないため、まずはできるだけ早めに相談をされることをおすすめします。