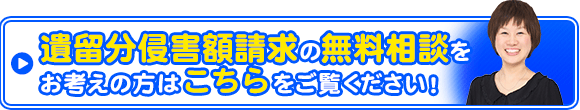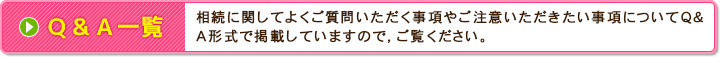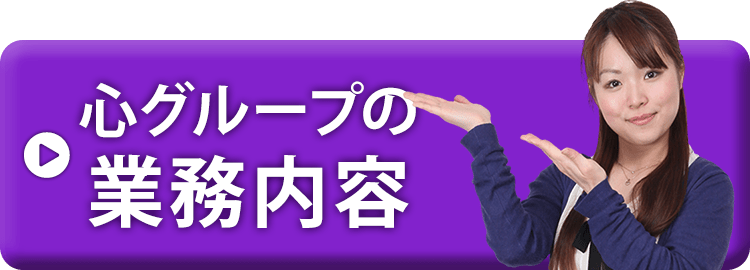遺留分と生前贈与
1 生前贈与によって遺留分が侵害されることがあります
遺留分は、遺産に対する最低限の権利です。
そのため、例えば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と記されていたとしても、遺留分権利者は遺留分を請求することができます。
また、上記のようなケース以外にも、「多額の生前贈与が行われたために遺産がほとんど無くなってしまった」場合など、生前贈与によって遺留分が侵害されることがあります。
このような場合は、生前贈与の分も遺留分の計算に用いる「遺留分の基礎となる財産」に加えなければ、遺留分が少なくなってしまいます。
そこで、一定の生前贈与については、遺留分の計算をする際に考慮されることとなっています。
生前贈与をお考えの際は、遺留分に配慮することが大切です。
遺留分の計算は複雑ですので、不安・疑問があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
以下では、遺留分の計算に含むことができる生前贈与について、ご説明いたします。
2 原則として相続開始1年以内の贈与が考慮されます
相続開始の1年以内に相続人以外へなされた贈与は、遺留分において、遺産の総額に含まれ、遺留分計算の対象となります。
例えば、被相続人であるAさんが、亡くなる半年前に友人のBさんに贈与した場合、その財産は遺産総額に含まれることになります。
3 1年以上前の贈与であっても考慮される場合
⑴ 遺留分を侵害することを知っていた場合
贈与する側と贈与される側が、遺留分を侵害することを知った上で贈与契約をした場合は、1年以上前までになされた贈与であっても、遺留分の計算の対象となります。
ただし、遺留分を侵害することを知っていたということを、裁判で証明するのは難しいケースもあります。
また、仮に大きな額の贈与をしたとしても、今後収入が見込めるような場合は、遺留分の侵害を知っていたとはいえないこともあります。
例えば、家賃収入があるような方の場合、ある時点で大きな生前贈与をしたとしても、今後の家賃収入によっては、遺留分の侵害が発生しない可能性もあるためです。
⑵ 相続人に対する生前贈与
相続人に対する生前贈与では、その贈与が特別受益に該当する場合、相続開始前の過去10年前までさかのぼって、遺留分の計算の対象とします。
特別受益とは、遺産の前渡しといえるほどの、ある程度高額な財産の贈与を指します。
例えば、Aさんが亡くなる8年前に、長男に2000万円の生前贈与を行い、相続開始時には100万円しか遺産が無いというような場合、長男は遺産の前渡しを受けたとして考えられるため、生前贈与の2000万円は、遺留分の計算において考慮されることになります。