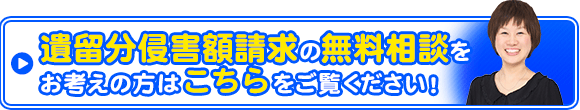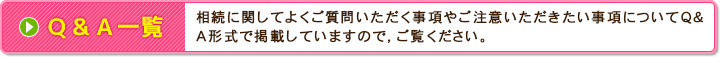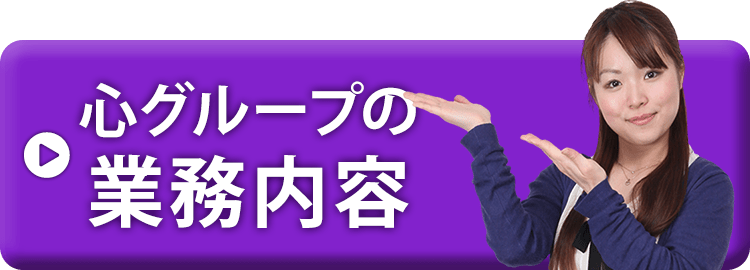遺留分と特別受益の関係
1 遺留分と特別受益は密接な関係があります
「遺留分」や「特別受益」といった言葉は、あまり日常的には使わないため、聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。
まずはそれぞれどのようなものなのか簡単にご説明します。
⑴ 遺留分
遺留分は、遺産を取得する最低限の権利のことを指します。
遺留分が請求できる例として、例えば父が亡くなり、1億円の遺産をすべて長男に相続させるという遺言書があったとします。
仮に相続人が長男と長女の2人だけだった場合、遺言書のとおりとすると、長女は遺産を全く受け取れないことになってしまいますが、この場合は遺留分として、長女は長男に2500万円を請求することができます。
遺留分としていくら受け取れるのかは、被相続人との続柄や遺産の額をもとに計算します。
⑵ 特別受益
特別受益は、亡くなった方から生前贈与を受けたり、遺言によって財産を相続したりしたことを指すものです。
例えば、先ほどの例で、父が生前、長女に2000万円の生前贈与をしていた場合、長女は遺産の前渡しとして2000万円を受け取ったと考えることができます。
そうすると、長女は、すでに2000万円を相続で取得したと扱われることとなり、遺留分の算定の基礎となる財産の額にその贈与も含めた上で遺留分を計算します。
この場合に長女が長男に請求できる金額は1000万円となり、遺留分として請求できる額が減ることになります。
このように、生前贈与が特別受益に該当する場合には、遺留分の計算の際にも影響が出ます。
特別受益がある場合の遺留分の計算について、詳しくは専門家へご確認ください。
2 どのようなケースが特別受益に該当するのか
すべての生前贈与が特別受益に該当するわけではありません。
特別受益に該当するには、あくまで、遺産の前渡しと評価できるくらいの、ある程度まとまった贈与であることが必要です。
例えば、長女が不動産を購入する際に父が1000万円の援助をしたというケースであれば、遺産の前渡しと評価できる場合が多いと思われます。
他にも不動産を贈与した場合や高額な貴金属を贈与した場合も、特別受益に該当する可能性が高いです。
一方で、父が長女に対して、毎月生活費を数万円援助していたような場合は、親子の扶養義務の範囲内と考えることができるため、特別受益には該当しないことが多いといえます。
3 生命保険は特別受益に該当するのか
例えば、父が全財産を長男に相続させ、長女には1000万円の死亡保険金を渡すようにしていた場合、この1000万円は特別受益に該当するのでしょうか。
実は、死亡保険金は、原則として受け取る人の財産であり、遺産とは考えられていません。
そのため、特別受益には該当しないとされています。
死亡保険金が遺産として遺産分割の対象となるかどうかについて、こちらでも解説していますので、参考にしてください。
ただし、死亡保険金の金額があまりに高額な場合は、遺産の一部と考えることもあります。
このように、特別受益に該当するかどうかは個別の判断が必要になる場合もありますので、お悩みの際は専門家に相談されることをおすすめします。