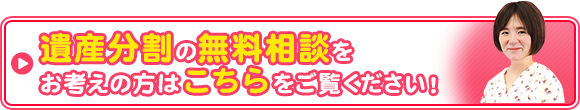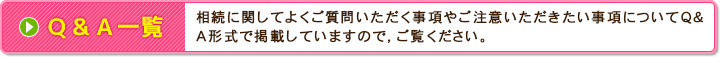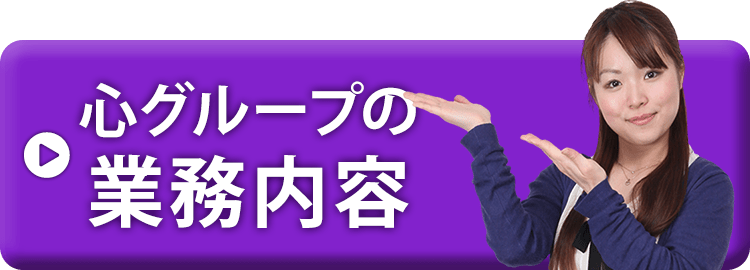遺産分割協議の方法
1 遺産分割協議とは何か
遺産分割協議は、簡単にいえば、相続人同士で遺産を分けるための話合いを行うことを指します。
亡くなった人が所有していた財産は、相続の発生により、原則として相続人全員で共有している状態となります。
しかし、遺産が共有されている状態のままだと、例えば不動産を売却することが難しくなるなどのデメリットが発生してしまいます。
遺産分割協議をしないとどうなるのかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
遺産の共有状態を解消するため、誰がどの財産をどのくらい所持するかを決める必要があります。
分け方としては、財産ごとに取得者を決めたり、誰か一人が取得する代わりに他の相続人に代償金を払うなど、状況によっていくつかの方法が考えられます。
一般的な遺産分割協議の方法としては、まずは話し合いから始まり、次のように進んでいきます。
2 相続人同士での話合い

まず、相続人で、遺産をどのように分けるのかを話し合うことになります。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけませんが、対面で協議する必要はなく、電話やメール、手紙のやりとりで行うことも可能です。
ただ、相続人全員で集まって話し合うことが多いため、例えば四十九日の席で、話合いがなされることもあります。
相続人同士で意見が合わず、当人同士での話し合いが進められない場合には、弁護士に間に入ってもらい、他の相続人との話し合いや交渉を進めてもらうこともできます。
以降でご説明するような、裁判所での手続きに入る前に、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
3 遺産分割調停
相続人同士での話合いで、遺産の分け方が決まらない場合は、遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割調停は、裁判所で行う話合いです。
具体的には、裁判所にいる調停員に間に入ってもらいつつ、双方の言い分を主張し、話合いで決着をつけることができないかを探っていく手続きです。
調停はあくまで話合いですので、遺産の分け方について双方が合意できない場合は、自動的に遺産分割審判へ移行します。
参考リンク:裁判所・遺産分割手続案内
4 遺産分割審判
遺産分割調停で決着がつかなかった場合、遺産分割審判という手続きへ進みます。
遺産分割審判は、話合いではなく、裁判官が遺産の分け方を強制的に決める手続きです。
そのため、遺産分割審判では必ずしも当事者の希望どおりに分け方が決まるとは限りません。
なお、審判の結果に納得がいかなかった場合には、即時抗告という手続きを行い、再度別の裁判官に遺産の分割方法について判断してもらうことが可能です。
単純承認したとみなされ相続放棄ができなくなる場合 死亡保険金は遺産分割の対象か