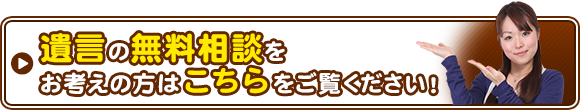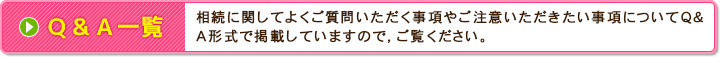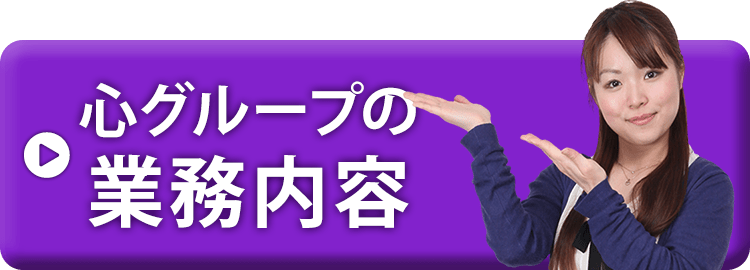遺贈と死因贈与は何が異なるのか
1 遺贈は1人で可能だが、死因贈与は1人ではできない
遺贈と死因贈与は、「亡くなったら、特定の人に財産権が移る」という点で、性質が似ていると言えます。
しかし、遺贈と死因贈与では「財産を渡す側が1人でできるかどうか」という点において大きな違いがあります。
まず遺贈は、遺言書に記載し、その後、遺言者が亡くなることで効力が発生するため、遺言者1人の意思で行うことが可能です。
他方で死因贈与は、「私が亡くなったらあなたにこの財産をあげる」という契約であるため、財産を渡す人と貰う人の合意が必要になります。
2 遺贈はやり方が決まっているが、死因贈与はやり方が決まっていない
遺贈をするためには、遺言の作成が必要です。
遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言に代表されるようにいくつかの種類があり、それに応じた作成方法が法律で定められています。
遺言の作成方法を守らずに作った場合には、原則として無効になってしまいます。
どのような場合に無効になってしまうのか、遺言で失敗してしまうケースを含めてまとめておりますので、こちらをご参照ください。
他方で死因贈与は、その形式が定められておらず、任意の方式で契約可能です。
例えば口頭で「私が亡くなったらこの自動車をあげる」と伝え、相手がそれに了承すれば、口頭での死因贈与契約が成立しますし、その他に書面やメール等でも死因贈与は可能です。
ただし、口頭での死因贈与契約は、他の相続人に贈与契約があったことを証明することができず、後日になって死因贈与の有効性を巡ってトラブルになるおそれがあります。
これを防ぐため、公正証書を作成したり、双方の実印と印鑑登録証明書を添付したりするといった対策をとるべきであるといえます。
3 遺贈はいつでも撤回可能だが、死因贈与は撤回できるとは限らない
遺贈の場合は、遺言書をいつでも、何度でも書き換えることができるため、遺贈はいつでも撤回ができるという性質があります。
遺言書の書き直しによって、遺贈の内容を変えるということも可能ですので、状況の変化に応じて、柔軟に対応できます。
他方で死因贈与は、その内容によっては、撤回ができない場合があります。