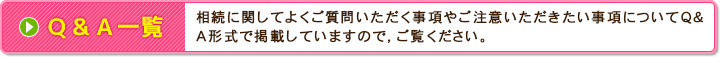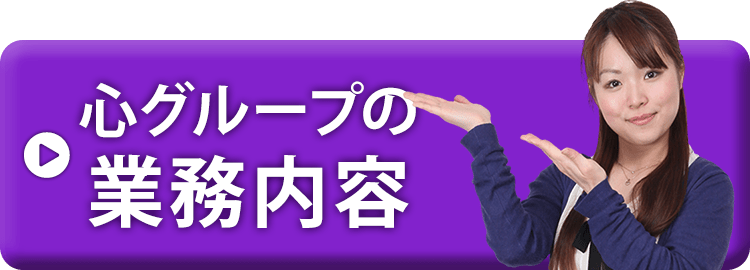寄与分が認められるための要件
1 相続人自身の寄与
寄与分とは、特別な貢献をした相続人に多くの遺産を渡すための制度です。
そのため、寄与分が認められるには、その相続人自身の寄与が必要になります。
2 特別な寄与と言える貢献をしたこと
法律上、家族間ではお互いに支え合うことが予定されているため、一般的な寄与では寄与分とは認められません。
例えば、「病院への付き添いを行っていた」、「一人では大変なので買い物の補助をしていた」などの、日常生活の簡易的なサポートのみであれば、歳を取った親の面倒を見ることは当然だとみなされ、特別な寄与とまでは言えないことが多いです。
他方で、寝たきりの父親を24時間体制で在宅介護するような場合は、家族なら行って当然という枠を超えた、特別な寄与と評価されることになります。
3 被相続人の遺産が維持されたか増加したこと
寄与分は、財産的な貢献が求められます。
例えば長女が父親の介護を頑張った場合、「本来であればプロに介護を任せるべきところを、長女の頑張りによってプロに介護を頼まずに済んで、結果として介護費用が節約できた」ということで、その節約分が財産的な寄与ということになります。
また、例えば長女が父親に対し長年仕送りをしていたり、家を建てるための費用や介護費用を負担していたりした場合には、その分父親がお金を使わずに済んだので、財産的な寄与があったということになります。
4 寄与分でお悩みの方は専門家にご相談ください
寄与分については、どのような貢献をしたのかを裏付ける資料を揃えることが難しく、遺産分割の際に寄与分を主張しても、他の相続人に納得してもらえず、相続人全員の話し合いがまとまらないケースが見受けられます。
寄与分がある場合の遺産分割についてまとめておりますので、こちらもご参照ください。
寄与分について相続人同士の意見がまとまらないような場合は、裁判所に寄与分を定める処分調停を申し立てます。
参考リンク:裁判所・寄与分を定める処分調停
寄与分は、その内容が日常的なサポートであったり、かなり前の事であったりすることが多く、証拠が少ないケースが少なくありません。
そこで、過去の裁判所の判断を精査し、どういった証拠がある場合に、どのような寄与分が認められるのかの見通しを立てて、立証活動をすることが重要です。
特に、寄与分の認定は、裁判官による裁量が大きいという特徴があります。
そのため、裁判官の個性や、裁判官が見ているポイントを注視して、適宜柔軟に方針を変えていくといった対応をとることも不可欠です。
このように、寄与分の主張をする際には、高度な法的知識や経験が不可欠になります。
寄与分でお悩みの方は、専門家に相談することをおすすめします。