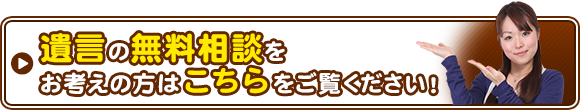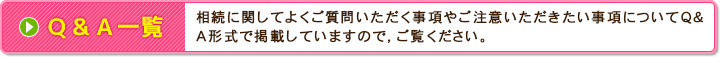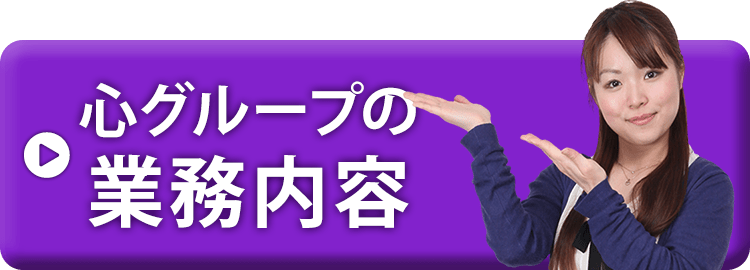遺言を作成するまでの流れ
1 財産の内容を把握する
遺言を作成するにあたって、メインになるのは、「誰にどの財産を相続させるか」ということです。
その前提として、自分がどのような財産を保有しているのかを把握しておく必要があります。
そのために、普段から使っているメインバンクのものだけでなく、長年使っていない預貯金口座や、証券会社の株式や投資信託、先祖から受け継いだ山林や農地など、保有している財産内容をすべて明らかにし、一覧表を作成することをおすすめします。
2 財産を渡す予定の人をリストアップする
財産の内容が把握できたら、次は、財産を渡す人のリストアップを行います。
例えば、相続人に財産を渡す予定で、相続人が長男と二男だったとします。
このケースでは、もちろん長男と二男がこのリストへ含まれることとなりますが、それだけでは不十分です。
もし、長男が自分よりも先に亡くなってしまった場合はどうするのかなど、不足の事態も想定し、対応を検討しておく必要があるからです。
もしも、長男が自分よりも先に亡くなってしまった場合は、長男に子がいればその子、つまり遺言者からみた孫に財産を渡すのかどうか、渡すのであれば、孫が複数人いた場合にはどうするのかといったことを検討しなければいけません。
そして、そのことを遺言に記載しておく必要があります。
このことを予備的条項といい、予備的条項はさまざまな状況を想定して作成する必要がありますので、遺言に関する知識があり作成に慣れている弁護士に相談されることをおすすめします。
また、相続人以外に、財産を渡したい人や寄付をしたい団体などがあれば、それもリストアップします。
3 誰にどの財産を渡すのかを検討する
財産を渡す人のリストアップができたら、次は、誰にどの財産を渡すのかを決めます。
財産の渡し方によって税金額が異なってくることもあるため、慎重な対応が必要となります。
例えば、配偶者が遺産を相続した場合に配偶者控除の特例を使うことができれば、1億6000万円までは相続税が課せられなくなります。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
4 遺言執行者を決める
相続が発生した後で遺言書の内容を実現する役割を担うのが、遺言執行者です。
遺言執行者は、遺言書どおりに、不動産の名義変更や預貯金の解約などを行います。
遺言執行者にはその他にも、財産目録の作成やそれぞれの相続人への報告といった義務があり、義務違反行為があると損害賠償請求をされる可能性もあります。
そのため、遺言執行者には法律の専門家を指定しておくと安心です。
遺言執行者の選び方についてまとめておりますので、こちらの記事も参考にご覧ください。
万が一、遺言書に記載された遺言執行者がすでに亡くなっていた場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることができます。
参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任
自筆証書遺言のメリット・デメリット 遺贈と死因贈与は何が異なるのか