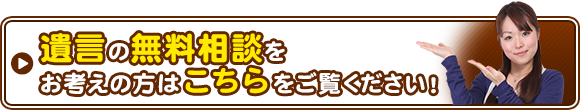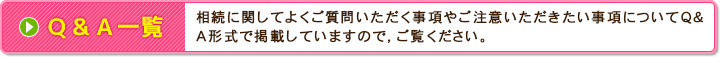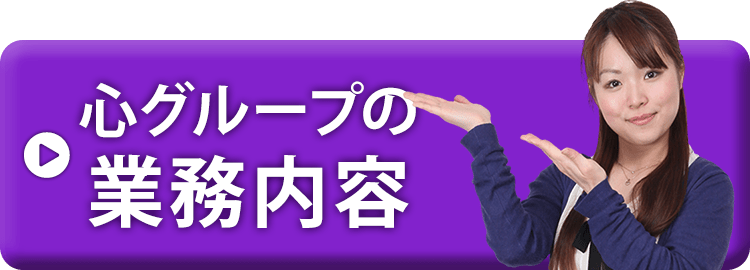遺言で失敗するケース
1 形式的なルールを守っていない場合
自筆証書遺言は、手軽に自分で作成でき、費用もかからないため、広く利用されています。
しかし、法律に定められた様式(財産目録を除き全文、日付、氏名を自筆で書く、押印をする、訂正のルールを守るなど)にもとづいて作成しないと、無効になってしまいます。
そのため、これらの様式をよく理解して作成する必要があります。
2 遺言の内容が明確でない場合
遺言の内容が明確でない場合は、執行ができなくなることがあります。
たとえば、対象となる不動産を特定できずに登記ができない、対象物件が漏れていて、別途遺産分割協議を行わなくてはならなくなるといったこともあります。
また、「金融資産1000万円は長女と次女で2分の1ずつ相続させ、残りは長男に相続させる」という内容の遺言を書くと、どの金融資産をどのように分けるかが明確でないため、トラブルのもとになってしまいます。
遺言を作成するときは、どの財産を誰にどれだけ相続させるのかを、明確にする必要があります。
3 不動産を共有にした場合
不動産は、できるだけ物件ごとに取得者を決めることが望ましいです。
共有にすると、建替や売却などについて意見が合わなくなることもあるほか、管理についても煩雑になり、さらに相続が発生して共有者が増えていくこともあるため、不動産を共有にすることはできるだけ避けた方がよいでしょう。
4 遺留分を考慮しなかった場合
遺言によって一人だけに相続させた場合、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
そのようなことを避けるためには、遺言を作成する段階で、遺留分についても考慮しておくことがよいでしょう。
遺贈と死因贈与は何が異なるのか 遺言執行者が必要な場合の選び方