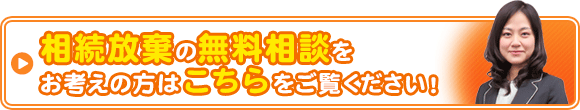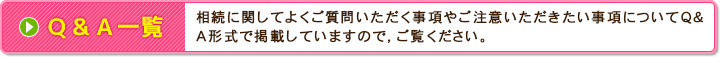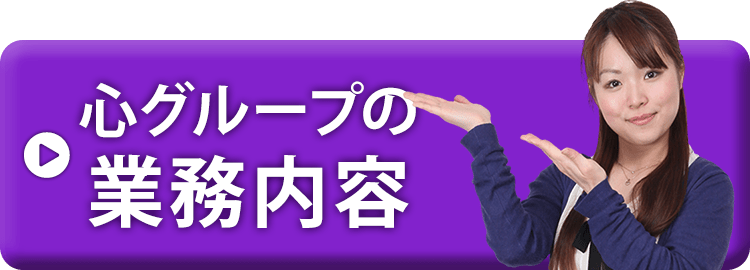相続放棄の必要書類
1 相続放棄に必要な書類
相続放棄には、以下の書類が必要となります。
- ・亡くなった方の戸籍謄本
- ・相続人の戸籍謄本
- ・亡くなった方の住民票
- ・相続放棄申述書
- ・期限を経過している場合のみ:事情の説明資料
それぞれの書類について、詳しくご説明していきます。
2 亡くなった方の戸籍謄本
相続放棄をする場合は、まず前提として「人が亡くなったこと」を裁判所に伝える必要があります。
裁判所は、市役所のデータを見ることができるわけではないため、その方が本当に亡くなったかどうかの判断ができません。
そこで必要となる書類が、戸籍謄本です。
亡くなった方の戸籍謄本を裁判所に提出することにより、ようやく「人が亡くなったこと」を伝えることができます。
そのため、相続放棄に必要な書類として、まずは亡くなった方の戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍は、市区町村役場で請求することができます。
参考リンク:京都市情報館・戸籍
3 相続人の戸籍謄本
「人が亡くなったこと」に加えて、「自分がその人の相続人であること」を裁判所に証明する必要があります。
相続人であることの証明も、戸籍謄本によって行います。
例えば、親子の相続であれば、子である自分の戸籍謄本に親の名前が記載されているため、親の戸籍謄本と自分の戸籍謄本を提出すれば証明が可能です。
他方、長男が亡くなって、その父親が相続放棄をする場合は、長男の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてそろえる必要があります。
これは、通常、第1順位の相続人は、長男の子(孫)となりますが、長男に子(孫)がいない場合は、第2順位の父親が相続人となるため、父親が相続放棄する場合は、「長男に子(孫)がいないこと」を裁判所に対して証明しなければいけないからです。
4 亡くなった方の住民票
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
どこの家庭裁判所で手続きを行うことになるのかというと、亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
そのため、亡くなった方の住民票を取り寄せて住所を確認し、その地域を管轄している裁判所に書類を提出することになります。
裁判所の管轄区域は、裁判所のホームページで確認できます。
参考リンク:裁判所・申立書提出先一覧(家庭裁判所)
5 相続放棄申述書
「相続放棄をしたい」旨を裁判所に伝えるための書面が、「相続放棄申述書」です。
書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
相続放棄申述書には、相続放棄をする理由や、遺産としてどのようなものがあるのか、債務がどれほどあるのかなどを記載します。
6 3か月が経過している場合の事情を説明する資料
相続放棄には、「亡くなったことを知ってから3か月以内」という期限が定められています。
通常、親族であれば、亡くなったという情報はすぐに伝わることが多いと考えられます。
しかし、亡くなった方が一人で遠方に住んでいたり、疎遠であったり等、何らかのご事情によって、例えば亡くなってから半年後にそのことを知ったということもあるかと思います。
その場合には、期限は亡くなった半年後から3か月以内となるわけですが、実際に亡くなったときとそのことを相続人が知ったときに大きくずれがあるため、なぜ半年後に知ったのか事情を説明するための資料が必要になることがあります。