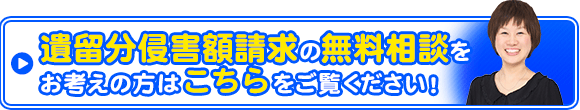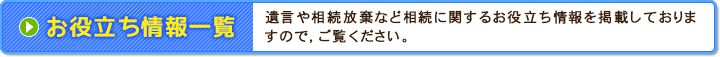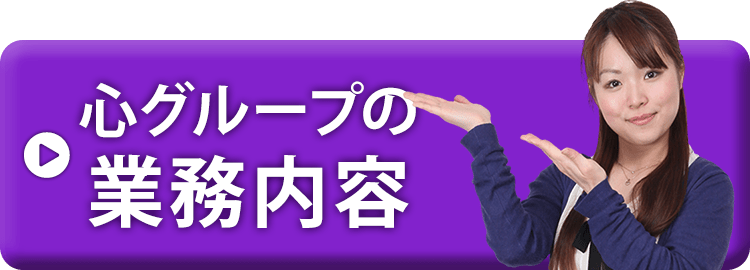遺留分を減らす方法に関するQ&A
「遺留分さえ渡すつもりはない」と遺言書に記載しておけば、遺留分をなくすことができますか?
遺留分は法律で守られた権利です。
一定の相続人が最低限の相続財産を受け取れるようにするためのものであり、これは遺言によっても覆ることはありません。
そのため、たとえ遺言書にどのような内容を記載したとしても、遺留分をなくしたり減らしたりすることはできません。
遺留分が侵害されている場合、相続人はその分を請求することができますし、相続人同士の話し合いで解決できなければ裁判所での調停などの手続きとなる可能性もあります。
参考リンク:裁判所・遺留分侵害額の請求調停
遺言書に「遺留分さえ渡すつもりはない」と記載したから、遺留分をなくすことができたと安心してしまわないようにご注意ください。
養子縁組による遺留分対策とは、どのようなものですか?
養子縁組を行い相続人の人数を増やすことで、遺留分を減らすことができるというものです。
例えば、相続人が長女と二女の2人で、長女に全財産である3000万円を相続させるというケースを考えます。
この場合の二女の遺留分は、遺産の4分の1にあたる750万円です。
他方、亡くなった方が長女の夫を養子にしていた場合、相続人は3人になり、二女の遺留分は遺産の6分の1にあたる500万円になります。
このように、相続人の数が増えれば増えるほど、1人あたりの遺留分の額は少なくなるため、遺留分を減らすことができます。
遺留分対策として養子縁組をするリスクはありますか?
遺留分を減らすための対策として挙げられる養子縁組ですが、この対策のリスクとして、養子縁組が無効だという裁判を起こされる可能性が考えられます。
養子縁組は、あくまで血縁関係にない2人が、親子の関係になることを認めるための制度です。
そのため、遺留分を減らすことだけを目的とした養子縁組は、親子関係を作る意思がないとみなされ、後で無効になる可能性があります。
生命保険を使った遺留分対策とは、どのようなものですか?
遺留分を減らす方法として、生命保険を使った対策もあります。
これは、預金を死亡保険金という形に変えておくことで、遺留分の額を減らすという方法です。
例えば、遺産が3000万円あって、相続人が長女と二女の2人だけだとします。
この場合、二女の遺留分は、遺産の4分の1の750万円です。
しかし、生前の間に300万円の預金で生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を長女に設定しておいたとします。
死亡保険金は原則として遺産ではないため、遺産総額は2700万円になり、二女の遺留分は4分の1の675万円になります。
このように、生命保険を利用すれば、遺留分を減らすことができます。
遺留分の期限に関するQ&A 生前からできる遺留分対策はありますか?