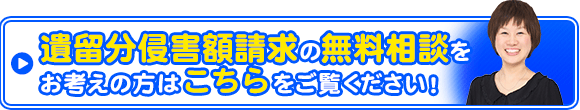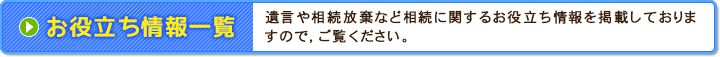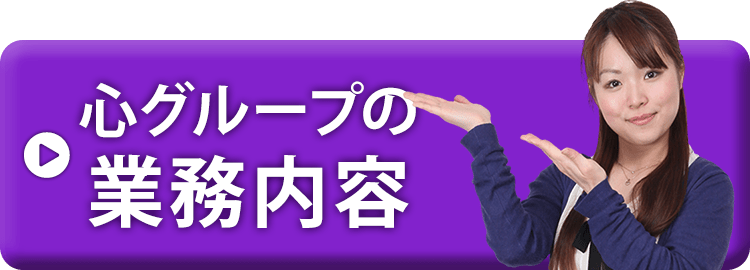遺留分の期限に関するQ&A
遺留分の請求には期限があるのですか?
はい、遺留分の請求ができる期間は決まっています。
遺留分を請求する権利は、「相続の開始」と「遺留分の侵害」があったことを知った時から、1年以内に請求をしないと、時効によって消滅します。
「相続の開始」とは、被相続人が亡くなったことを指します。
「遺留分の侵害」とは、特定の人に多額の生前贈与をしたり、遺言書で特定の人に遺産を渡したりといったことなどにより、自己が最低限もらえるはずだった遺産をもらえなくなったことを指します。
「相続の開始」と、「遺留分の侵害」を知った時から、1年という期限がある以上、例えば1周忌を待ってから請求するというような対応は避けなければなりません。
時効期間が経過すると、遺留分を侵害した人が時効の援用(時効の効果を主張する意思表示のこと)をすることで、遺留分侵害額請求が認められなくなってしまいます。
遺留分の期限は10年だと聞いたことがありますが本当ですか?
ご事情によっては、遺留分の期限が10年となるケースもあります。
「相続の開始」、つまり被相続人が亡くなってから10年が経過すると、遺留分を侵害した人が消滅時効の援用をしなくても、遺留分の権利は消滅します。
仮に、ご家族が亡くなったことを知らなかった場合や、遺留分の侵害を知らなかった場合であっても、ご家族が亡くなってから10年が経過することにより、遺留分の権利は消滅してしまいます。
遺留分の期限の前に口頭で「遺留分を請求する」と伝えれば問題ありませんか?
遺留分の請求方法に決まりはないものの、口頭でのみ遺留分の請求を伝えるという対応は、後で裁判になった際に敗訴する可能性があり、非常にリスクが高い対応方法であるといえます。
後になって、相手方から「遺留分の請求をされたことはない」と主張された場合、期限内に遺留分の請求をしたことを証明する必要があります。
しかし、口頭で相手方に伝えただけでは、物的な証拠がないため、期限内に遺留分の請求をしたことの証明ができない可能性が高いです。
遺留分の請求をした証拠はどのように残せばいいですか?
一般的には、内容証明郵便で遺留分の請求を行うという方法をとります。
参考リンク:郵便局・内容証明
内容証明郵便を利用すれば、いつ、どんな内容の書類を送ったかを、証明することができるため、遺留分の請求をした証拠として、非常に強力な証拠になります。
もっとも、相手方が内容証明郵便の受け取り拒否をするようなケースも考えられるため、メールやSNSで遺留分の請求の意思を伝えたり、遺留分を請求することを口頭で伝え、録音したりするという方法もあります。
しかし、これらのデータは、いつ消えてしまうか分からないことや、偽造の可能性などを主張されることもあるので、十分とはいえないかもしれません。
そこで、あわせて普通郵便でも遺留分の請求をしたうえで、期限内に裁判所に訴訟を提起するのがよいでしょう。
相手方の住所が分からない場合、どうやって遺留分の請求をすればいいでしょうか?
相手方の住所が不明である場合は、内容証明郵便を送ることができません。
その場合、相手方の住所について、戸籍の附票や住民票を取り寄せるなどして調べることが一般的ですが、相手方が住民票の住所地にいない場合もあります。
仮に、勤務先が分かれば勤務先に送ることもできますが、勤務先も分からず、その他の方法でも住所が分からないような場合は、裁判所で掲示版に掲示することで送達の効力を発生させるという方法(公示送達)もあります。
そのようなケースでは、裁判所に訴訟を提起し、相手方の住所が不明で勤務先も分からないことを報告書にまとめて申し立てを行うことで、相手方に直接遺留分の請求の意思を伝えることができなくても、期限の問題をクリアすることはできます。
ただし、遺留分の期限が過ぎてから、裁判所に訴訟を提起しても、すでに時効になっていることに変わりはないため、注意が必要です。
遺留分の請求はするつもりですが、そもそも遺言が無効だと思っています。1年以内に「遺言が無効だ」という裁判をすれば、遺留分の期限はクリアできますか?
「遺言が無効だ」という裁判をしても、原則として遺留分の請求をしたことにはならないため、遺留分の期限をクリアすることはできません。
そもそも、遺言の無効の裁判と遺留分の裁判は、全く別の裁判なので、遺言の無効裁判をしても、遺留分の期限を守ることにはなりません。
特殊な事例では、遺留分の期限を緩やかに解釈した判例がありますが、その事例はあくまで例外的なものです。
そのため、遺言無効の裁判をする場合は、遺留分の裁判も同時に行い、遺留分の期限を別途クリアすることが大切です。
一度請求をしておけば、遺留分が時効になる心配はありませんか?
遺留分を請求した後も、時効には注意が必要です。
平成30年の民法改正により、遺留分の法的性質が金銭債権となり、通常の金銭請求と同様、5年で時効になると定められました。
そのため、いったん遺留分侵害額請求の意思表示をしたとしても、そのまま長期間何もしないような状態が続いた場合、本来取得できるはずであった金銭を取得できなくなる可能性がありますので、交渉や調停、訴訟などで実現していく必要があります。
期限を過ぎてから遺留分を請求された場合はどうすればよいですか?
遺留分を請求されたときに、消滅時効が成立している場合は援用することで、請求に応じる必要はなくなります。
ただし、時効が成立しているかについては慎重に判断しなければなりません。
相続放棄の流れに関するQ&A 遺留分を減らす方法に関するQ&A