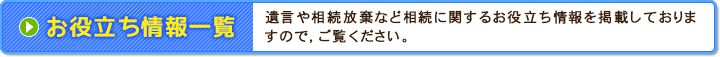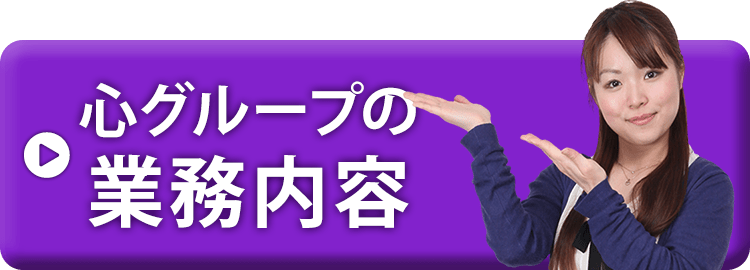相続に必要な戸籍謄本の集め方についてのQ&A
相続に必要な戸籍謄本はどのようなものですか?
相続に必要な戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の現在戸籍です。
相続人が先に亡くなった場合には代襲相続が発生し、亡くなった方についても出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいるかを確認し、離婚したり再婚したりしている場合には、前配偶者との間に子がいるかどうかを確認し、相続人を確定することになります。
ただし、公正証書遺言がある場合は、遺産を受け取る人は遺言書に記載されているため、相続人の調査をする必要はなく、遺言者の死亡時の戸籍のみで足ります。
相続に必要な戸籍謄本をまとめて取得することはできますか?
令和6年3月1日から、戸籍謄本に関する広域交付制度が始まり、相続に必要な戸籍謄本について、最寄りの市区町村の窓口でまとめてとれるようになりました。
具体的には、本人の戸籍謄本のほか、配偶者(夫又は妻)、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍謄本がとれるので、かなり便利になりました。
この広域交付制度は、郵送や代理人では利用できず、本人が窓口に行って顔写真付きの身分証明書を出す必要があります。
また、兄弟姉妹、おじ・おばなどの戸籍謄本等は取得することができないので、その分は別途集める必要があります。
なお、この制度で取得できるのはコンピューター化されている戸籍謄本・除籍謄本のみであるため、コンピューター化されていないものは対象外となります。
参考リンク:京都市情報館・戸籍証明書等の広域交付について
最寄りの市区町村の窓口で取得できない分は、どのようにして取得すればよいのですか?
前記の方法以外では、従来どおり本籍地のある市区町村役場に申請して集めることになります。
本籍地が不明なときは、先に住民票又は住民票の除票を取得すると、本籍地を調べることができます。
死亡時から出生時まで順番に、「改製」や「転籍」などの情報をもとに、一つ前の戸籍にさかのぼっていく作業を繰り返して集め、最終的には相続人を確定することになります。
農地の相続に関するQ&A 相続人と連絡が取れない場合のQ&A