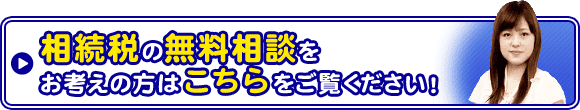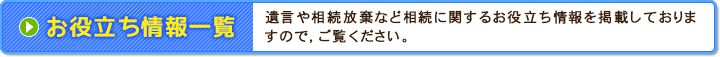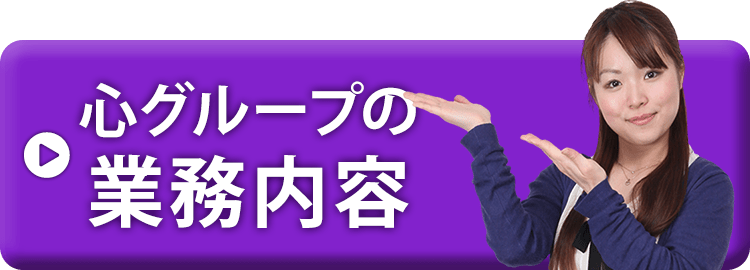小規模宅地等の特例についてのQ&A
小規模宅地等の特例とは、どのような制度ですか?
相続税の負担を大幅に減らすことができる制度です。
亡くなっていた方が居住していた土地や、事業で使用していた土地がある場合に、一定の条件を満たすと、相続税を大幅に減らすことができます。
この特例を受ける際には、相続税の申告書に小規模宅地等の特例の適用を受けようとする旨を記載すること、必要書類を添付することが必要です。
なぜ、小規模宅地等の特例を使うと、相続税を減らすことができるのですか?
相続税申告上、土地の価値を下げることができるからです。
相続税は遺産に対して課税されます。
遺産の額が大きいほど、相続税の額も増えていきます。
反対に、遺産の額が少ないほど、相続税の額は少なくなります。
参考リンク:国税庁・相続税の税率
ということは、5000万円の土地を相続した場合より、1000万円の土地を相続した方が、相続税は少なくなります。
ここで、本来なら5000万円の土地を、「相続税申告をする際だけ、1000万円の土地ということにしよう」というように取り扱うことができれば、相続税の額が少なくなります。
これを法的に可能にするのが、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例が使える条件は何ですか?
様々なパターンに応じて、条件は変わります。
代表的な条件としては、亡くなった方が居住していた土地であったり、亡くなった方が事業のために利用していた土地であったりすることが必要です。
つまり、亡くなった方が全く利用していなかった、遠方の別荘地などに対しては、小規模宅地等の特例は使えないということです。
また、厳密には、亡くなった方が利用していた土地だけでなく、亡くなった方と生計を同一にしていた親族が、居住や事業で利用していた土地も条件に当てはまります。
どれくらい土地の評価額が下がるのですか?
土地の種類によって、最大80%下がります。
亡くなった方が居住していた土地については、330㎡の範囲内で、評価額が80%下がります。
亡くなった方が事業に使っていた土地については、400㎡までの範囲で、評価額が80%下がることとなります。
亡くなった方がアパートなどを経営していた場合の土地については、200㎡までの範囲で、評価額が50%下がります。
参考リンク:国税庁・小規模宅地等の特例
相続税の計算方法に関するQ&A 相続を円満に解決したいのですが,弁護士に依頼するとトラブルが大きくなりませんか?