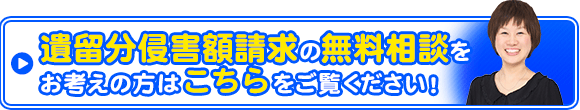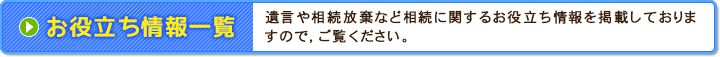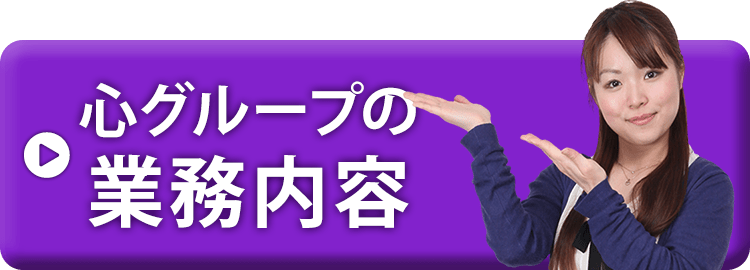生前からできる遺留分対策はありますか?
1 遺留分対策となる方法の概要
私に万が一のことがあった際に、娘一人に全財産を残してあげたいと考えています。
その際に、他の相続人に遺留分が発生すると思うのですが、生前にこの遺留分の対策をすることはできるのでしょうか。
このように、生前に遺留分の対策を行いたいというご要望はよくあります。
生前に遺留分を減らしていく方法としてよく活用されるのは、以下の方法です。
① 養子縁組
② 生前贈与
以下でこれらの方法について、具体的に解説していこうと思います。
2 養子縁組
まずは、養子縁組が遺留分対策になるメカニズムを解説します。
遺留分の割合は、子や配偶者が相続人にいる場合には、
法定相続分×2分の1
となるとされています。
この時、法定相続分については、相続人が増えるほど少なくなっていくという性質があります。
例えば、相続人が子2人のみの時には、法定相続人が各2分の1となりますが、養子を1人加える事で、法定相続分は各3分の1となります。
そうすると、前者の場合には、遺留分が4分の1になるのに対して、後者の場合には、6分の1となるのです。
そのため、養子縁組を行うことで子の数が増え、その分法定相続分が小さくなるため、遺留分対策となることがあります。
3 生前贈与
⑴ 生前贈与が遺留分対策となるメカニズム
もう一つ活用される方法としては、生前贈与が挙げられます。
生前贈与が遺留分対策となるメカニズムとしては、遺留分の具体的な計算式に原因があります。
遺留分の金額は、
遺産総額×遺留分割合
によって求められます。
その際、遺留分の基礎となる「遺産総額」には、被相続人が生前に贈与した金額を持ち戻すこととされていますが、相続人に対して行われた贈与は原則として10年分持ち戻すのに対して、相続人でない者に対して行われた生前贈与は原則として1年分持ち戻すこととされています。
例えば、被相続人が10年間息子と息子の妻に110万円ずつ渡していた場合、息子に対する贈与は10年分を持ち戻すのに対して、妻に対する生前贈与は1年分持ち戻せばよいのです。
そのため、息子側としては、相続人でない親族に多くの生前贈与を受ける事で遺留分の対策ができるようになるのです。
⑵ 遺留分対策として生前贈与をする際の注意点
では実際に生前贈与を遺留分対策として行っていく際に注意する点は、どのような点でしょうか。
まずは、暦年贈与の非課税枠(年110万円)の範囲内で毎年1回行うように注意するという点です。
この110万円の非課税枠を超えた場合には、翌年の3月15日に贈与税の申告を行い、贈与税を納める必要があります。
そのため、この非課税枠の範囲内で贈与を行うように調整することが必要となるのです。
また、贈与契約書を毎回作成するように注意し、振込先の口座は受贈者が常用している口座にする必要があります。
相続税申告を行う際に、被相続人の名義預金が無いかという点はかなり注意深く調査されます。
そのため、贈与契約書を作成して贈与の証拠を残すとともに、名義預金とならないように常用の口座に振込をすることが必要です。
遺留分を減らす方法に関するQ&A 相続登記だけでもお願いできますか?