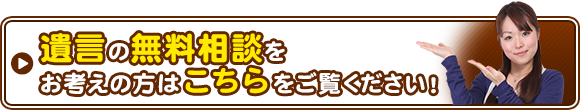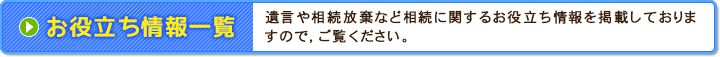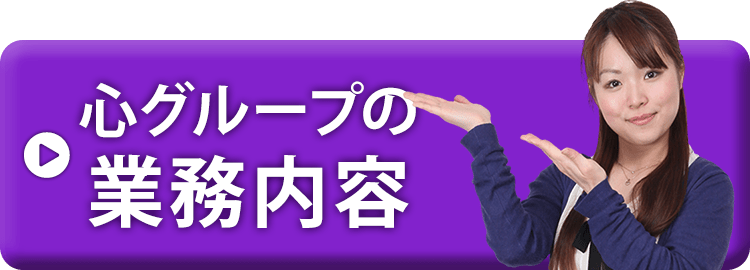遺言の証人に関するQ&A
遺言をする際に証人は必要ですか?
遺言の種類によって、証人が必要かどうかは異なります。
遺言者が手書きで作成する「自筆証書遺言」については、証人は不要です。
その点で、自筆証書遺言は、遺言書を書きたい人が1人で作成することができるという手軽さがあります。
対して、自筆証書遺言以外の方法で遺言を行う場合には、証人が必要となります。
具体的には、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、法律で、2人以上の証人の立会いが必要であるとされています。
なぜ証人が必要なのですか?
間違った遺言が作成されることを防ぐためです。
公正証書遺言は公証役場で公証人の手によって書かれ、秘密証書遺言は公証役場へ作成した遺言書を持ち込み、遺言書の存在を認証してもらうこととなります。
したがって、遺言が間違いなく本人のものであることや、正常な判断のもと本人の意思によって作成されているかなどを確認するため、証人が必要となるのです。
例えば、Aさんが公証役場で遺言書を作成することになった場合、作成に携わる公証人は、公証役場に来た方が本当にAさんかどうかまでは分かりません。
そのため、公証人に免許証や印鑑登録証明書などの本人確認書類を見せて、本当にAさんであること、つまり「人違いがないこと」を確認します。
さらに証人にも確認してもらい、二重で確認をします。
また、判断能力が低下した人が、言われるがままに遺言書を作成していないかどうかについても、公証人と証人が二重に確認することになっています。
遺言の証人は誰でもよいのですか?
法律上、証人になることができない人がいます。
仮に、AさんがBさんに全財産を相続させるという遺言書を作成する場合、その場にBさんが証人として立ち会うとしたら、どのようなことが起こり得るでしょうか。
他の相続人からすれば、「BさんがAさんを誘導して、自分に有利な遺言書を作成させたのではないか」という疑いが出ても不思議ではありません。
そのような疑いを生じさせないために、相続において利害関係がある人は証人になることができません。
具体的には、相続人になる予定の人、遺産をもらうことになっている人、それらの配偶者や子どもなどです。
また、その他にも未成年者や、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記および使用人等、法律上証人になることができないとされている人がいます。
証人になることができない人が立ち会った場合、遺言の効力はどうなりますか?
原則として、遺言は無効になります。
法律上、証人になることができない人が証人になって作成された遺言は、その内容のすべてが無効になります。
他方、適正な証人が一人立ち会ったものの、さらにもう一人の証人として、証人になることができない人も立ち会った場合はどうでしょうか。
この場合は、ただちに遺言が無効になるわけではありませんが、一定の場合には遺言全体が無効になることもあるため、注意が必要です。
証人は誰に頼むべきですか?
利害関係がない第3者が望ましいかと思います。
何らかの形で利害関係を持っている人が証人になると、その証人が適正に証人としての業務をしたのかということに対し、疑いや疑問が生じる場合があります。
そのため、証人は、利害関係がない第3者に頼むべきであるといえます。
なお、ご自分で証人を探すのが難しい場合には、公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。
証人の費用はどれくらいかかるのですか?
誰を証人にするかによって、費用が変わります。
例えば、公正証書遺言を作成する際、公証役場に証人の用意を依頼することが可能です。
公証役場が用意した証人には、1万円前後の費用を支払う必要があります。
他方で、知人や、遺言書の作成を依頼した専門家に証人を依頼し、証人側が費用はいらないと言った場合、証人の費用は不要です。
自筆証書遺言の注意点に関するQ&A 遺言書の開封方法に関するQ&A