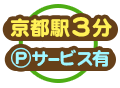遺言書の書き方
1 手書きの遺言書の書き方
手書きの遺言書を作成する場合、必ず記載しなければならないことや注意すべきポイントが4点あります。
⑴ 原則として全て手書きであること
手書きの遺言書は、文字通り自分の手で書く必要があります。
仮にパソコンで遺言書を作成した場合、印鑑を押したとしても、その遺言書は無効になります。
例外的に、財産目録だけは、手書きだと作成が大変なため、パソコンなどで作成することが認められています。
もっとも、財産目録には、各ページに署名・押印が必要になる等、細かいルールがあります。
なお、手書きであれば、外国語で作成した遺言書も有効です。
⑵ 日付を記載すること
手書きの遺言書を作成する際、忘れがちなのが作成した日付です。
日付を記載していないと、その遺言書は無効になります。
日付は、「いつ、その遺言書を作成したのか」が分かればいいため、「私の70歳の誕生日」といったような記載でも有効ではありますが、無意味にリスクを負うことは避けた方がよいので、暦上の日付を記載した方がよいでしょう。
もし、「令和4年1月吉日」といった記載をすると、日付の特定ができないため、遺言書は無効になります。
⑶ 署名をすること
誰が書いた遺言書なのかを明らかにするため、署名が必要です。
あくまで、遺言者を特定するためのものなので、必ずしも戸籍上の指名である必要はありません。
例えば、通称名やニックネームなどでも、誰が遺言者か特定できれば問題はありません。
⑷ 押印をすること
手書きの遺言書を作成する場合、押印が必要になります。
押印は、どのような印鑑でもよいため、必ずしも実印を使う必要はありません。
ただし、後になって、別人が押印したと主張する人が現れた時のために、実印の押印が望ましいでしょう。
2 公正証書遺言の書き方
公正証書遺言は、証人2名の立ち合いのもと、公証人が遺言書を作成することになります。
公証人は、遺言者から遺言内容を聴き取り、それを法的文書にします。
公正証書遺言自体は、公証人が作成するため、書き方で困ることは少ないというメリットがあります。
ただし、公証人はあくまで言われた通りの内容の遺言書を作成するのみなので、必ずしも、紛争防止や税金面での考慮までなされるとは限らないため注意が必要です。